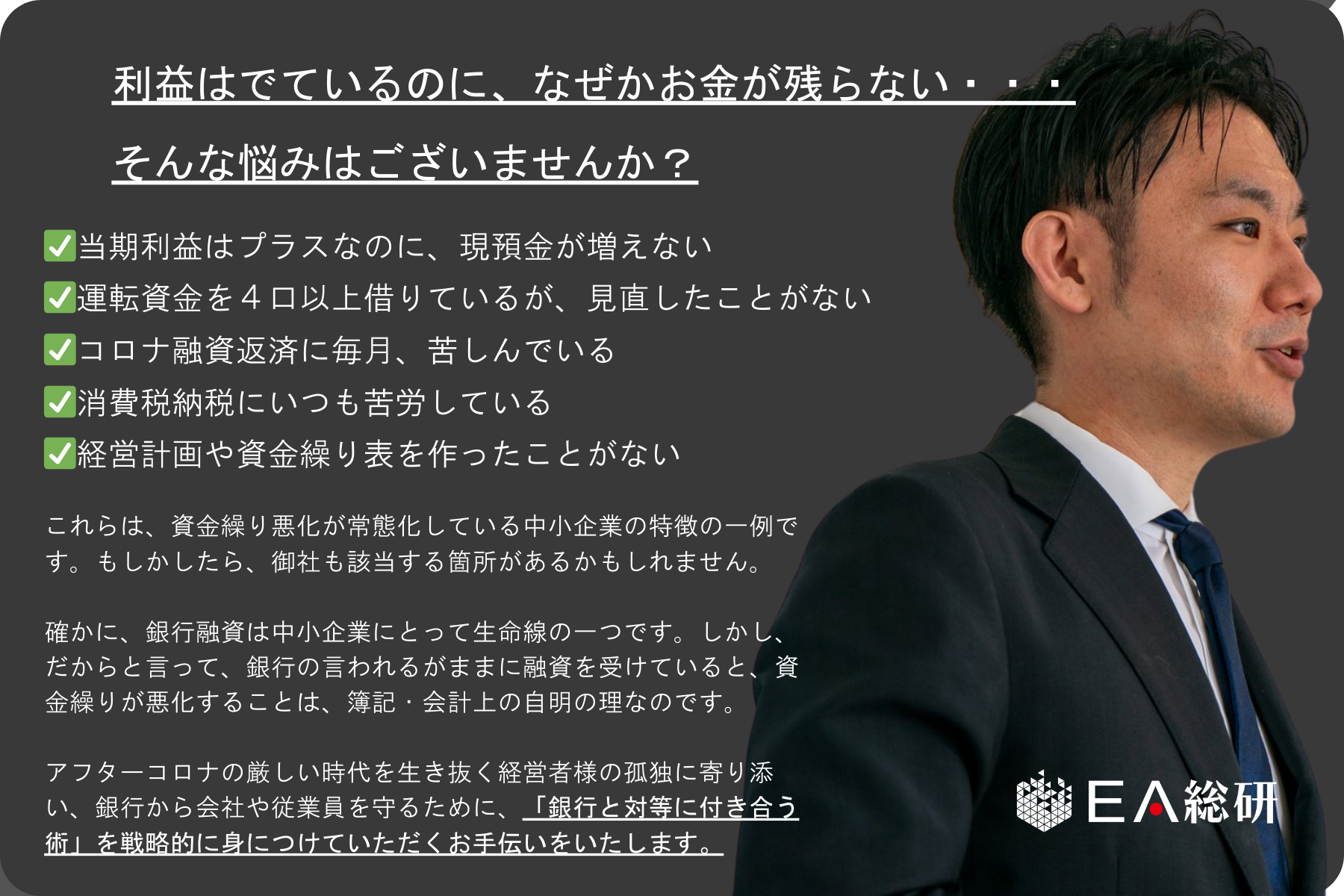
【アフターコロナの銀行融資戦略】コロナ融資の借換保証制度で今までと変わったこと
空前のコロナ融資の返済に苦しむ中小企業様も多いことでしょう。そこで借換を考える方も多いと思いますが、コロナの借換は従来通りの借り方ではうまくいきません。作成する書類が増えましたし、何より、銀行側が採用する融資方針が全く変わっているのです。ここをキャッチアップしているか否かで、今後の融資戦
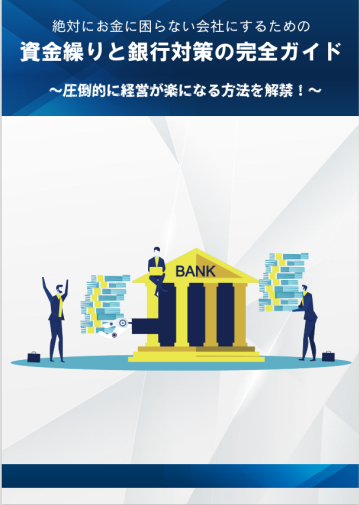
私は10年近く、金融の世界に身を置いていますが、成績の優劣を問わず、多くの金融マンが税務知識を武器に経営者に貢献しているように感じています。それは決して悪いこととは言いません。経営者に限らず、支払う税金が減ることは嬉しいものです。
しかしながら、「税の徴収」とは国家政策の一環であり、「節税」が経営や経営判断の本質ではありません。もちろん、昨今の増税政策には異を唱えたい気持ちは私にもありますし、実際に、税務知識が余計なキャッシュ流出を抑えることができることも事実です。そうだとしても、そうだとしても、お伝えしたいことがあるのです。
確かに、節税は、直ちに経営に悪影響はないかもしれません。しかし、節税視点から金融商品(銀行・保険・証券)を選択すると、経営に悪影響を与えます。なぜなら、節税とは、経営視点では利益を減らす行為であり、故に銀行は「節税が大嫌い」だからです。ですから、過度な節税は銀行からの評価を著しい低下を招き、本当にお金を借りたいときに借りられない・・・、慢性病のようにジワジワと後から苦しくなるのです。
しかしながら、経営者に身近な存在である士業・金融マンが「税務」と「財務(=経営)」の違いを理解していない現状こそ、非常に悲嘆すべきことであり、その結果、経営者を支援する専門家が不在のまま、中小企業の資金繰りの悪化に歯止めがかからないのです。
EA総研のサポートの土台は「税務」ではなく、「財務=経営」です。財務の視点を手に入れた経営者は、お金の使い方が一変します。経営とお金の密接なリンクが目に見えて初めて、経営者の行動が変わるのです。
従来の融資体制は「決算書」や「担保」が中心でした。しかし、金融機関のお上である金融庁は今、融資に対して大きな舵を取っています。それがR8年から始まる「企業価値担保権」であり、これは2015年の「事業性評価融資」に端を発します。難しい言葉が並ぶので、誤解を恐れずに、ざっくり、大きく、簡易に言い換えると、「未来に対して明確な経営計画と経理体制を持つ企業だけに、融資しますよ」と、金融庁が言い始めているのです。
コロナの借換保証制度、早期経営改善計画書類、(旧)政府系金融機関の融資申込書類一式をご覧になってみてください。融資申込企業の決算書の提出にとどまらず、自社の強みや弱み、外部環境の変化、取引企業の比重、それらを戦略的に数値に落とし込んだ損益計画と資金繰り表の提出を求められています。
日本の資金調達体制は大きな変化の渦中にいます。不確実性の高い時代の環境変化に飲み込まれず、未来に対して明確に手を打つことのできる中小企業以外は、お金が借りられない時代が到来しています。

平成は昭和の延長でした。令和はニューノーマルが始まります。困ったことに、この変化は金融機関にも正しく伝わっていません。ですから、経営者にも正しい情報が伝わらず、お金が借りられない企業が急増しているのです。
EA総研の情報提供は、国の要請を主眼に置いているため、大きく本質を外すことは少ないでしょう。中小企業の心臓であり、血液の役割である銀行融資を制する経営者が、アフターコロナを生き抜く存在の先駆けとなると信じています!

団塊の世代が75歳以上を迎える・・・いわゆる2025年問題。2025年問題は、医療や介護等の社会保障制度への関心を集めますが、中小企業の事業承継問題も内包しています。M&Aも盛んに行われていますし、生命保険を活用して株価を引き下げ対策を行っている企業も少なくないでしょう。
しかし実際は、後継者に引き継げない会社、清算したくても清算できない会社が4割を超えるとご存じでしたか。これら4割の会社は、たとえ、決算書の数値上は債務超過ではなくても、「実態評価」した場合に、銀行が債務超過と判定する企業なのです。経営者も税理士も、自社の決算書の数値をそのまま信じて評価(これを簿価評価と言います)しますが、銀行の評価基準は時価です。時価は市場原理に基づくので、非常に厳しい評価です。銀行は、決算書に並ぶ売掛金や在庫、貸付金や仮払金、土地や建物を、「実態価値(時価)」に評価し直してから融資の判断を下します。
単刀直入にお聞きします。あなたの会社は、会社の資産を全て時価で清算したとしても、借金を全て返せますでしょうか。もしくは、後継候補者が引き続き融資を受けられる財務指標を維持できるか計算してから、株価や退職金の金額を計算していますでしょうか。
物事の最後の最後に大きく揉める事態は、人生に大きな後悔をもたらします。そうならないように、あらゆる経営計画を「実態価値(時価)」に基づいて立案しなくてはならないのです。
EA総研のサポートは、「実態評価(時価)」に基づいたものであり、真の意味で会社を強くするものであり、経営者としての集大成である勇退を有終の美で飾るように、お約束します。
銀行融資に特化し、資金繰り改善に貢献する限定動画を配信します。
空前のコロナ融資の返済に苦しむ中小企業様も多いことでしょう。そこで借換を考える方も多いと思いますが、コロナの借換は従来通りの借り方ではうまくいきません。作成する書類が増えましたし、何より、銀行側が採用する融資方針が全く変わっているのです。ここをキャッチアップしているか否かで、今後の融資戦
経営計画を作りたいけど、作り方が分からない・・・こういった相談をよく受けますし、かつての私もそうでした。しかし!経営計画はもっと以前の問題で、「作らないと、経営できない」ということを知らなかったのです。なぜ、経営計画を作らないといけないのか?その理由についてお話します。資金繰り改
銀行員から「損益計画」や「資金繰り表」の提出を求められたことはありますか?銀行が事業性評価融資に取り組むちょうど過渡期の今、銀行も融資の仕方を変えてきています。事実、コロナの借換融資や短期継続融資を借りる時は、このような書類の提出を求められます!この機会に、根拠のある損益計画の作り方を学
含み損益という言葉を御存じでしょうか?銀行は、実は、経営者が提出してきた決算書をそのまま信じていません。必ず、「含み損益」を確認してから、銀行格付けをしています。「含み損益」の確認の仕方を、共に学びましょう。資金繰り改善に関する有料個別相談↓【個別相談お申込みはこちらをクリッ
銀行員が融資の際に、絶対に見たくない3勘定があります。なぜなら、この3勘定を見つけたら、銀行は融資したがらないからです。この3勘定の正体について、迫ります!資金繰り改善に関する有料個別相談↓【個別相談お申込みはこちらをクリック】富山県内商工会議所にて毎月開催のセミナーのご案内
EA総研による財務コンサルティングのご案内。銀行融資アドバイスを土台に、資金繰りを改善し、自発的に経営計画策定や資金繰り管理ができるようになって初めて、銀行員と対等に交渉できる状態になるのです。
EA総研では元銀行員のコンサルタントと連携しており、銀行取引と資金繰り改善をサポートします。20年を超える業歴を持つ、北関東の大手金融機関出
【元銀行員コンサルタントと協同】「銀行取引アドバイス」+「資金繰り改善」のサポート
4つのサービスの料金をご紹介します。サービスへのお申込みは各詳細フォームのページからご入力ください。※決済方法はクレジットカード
コンサルティングサービス4つの料金体系
現在準備中です
確定拠出年金の導入支援
Flow To Contact契約の流れについて以下、契約までの流れをご案内いたします。ご依頼時の参考とされてください。またご相談内
契約までの流れ
中小企業支援者の道、つまり時代と経営者から求められる会計事務所への道を共に歩みましょう!
会計事務所の皆さまへ:私が中小企業支援を共有する理由中小企業の経営者が抱える最大の悩みが「資金繰り」にあることは、周知の事実でしょう。この問題を解決するために奔走する私ですが、中小企業を支援の道を歩む中で気づいたことがあります。それは、 私一人では支援できる企業数に限界がある ということです
会計事務所様対象:オンラインセミナーのご案内「なぜ銀行融資アドバイスで、月額10万円の顧問料に上がるのか」記帳代行だけでは生き残れない!これからの会計事務所に求められるのは、記帳代行や税務申告の枠を超えた 「付加価値」 を提供する力です。中小企業経営者が真に必要とするサポートとは
関与先様への貢献度向上を図る会計事務所様へ無料進呈アフターコロナを生き抜く中小企業を支える会計事務所様にこそ読んでいただきたい!なぜ1顧客当たりの報酬が高い会計事務所は”財務コンサル”を提案しているのか下記内容をご記入いただきお申込みください。お申込みいただいた方に小冊子「なぜ1顧客